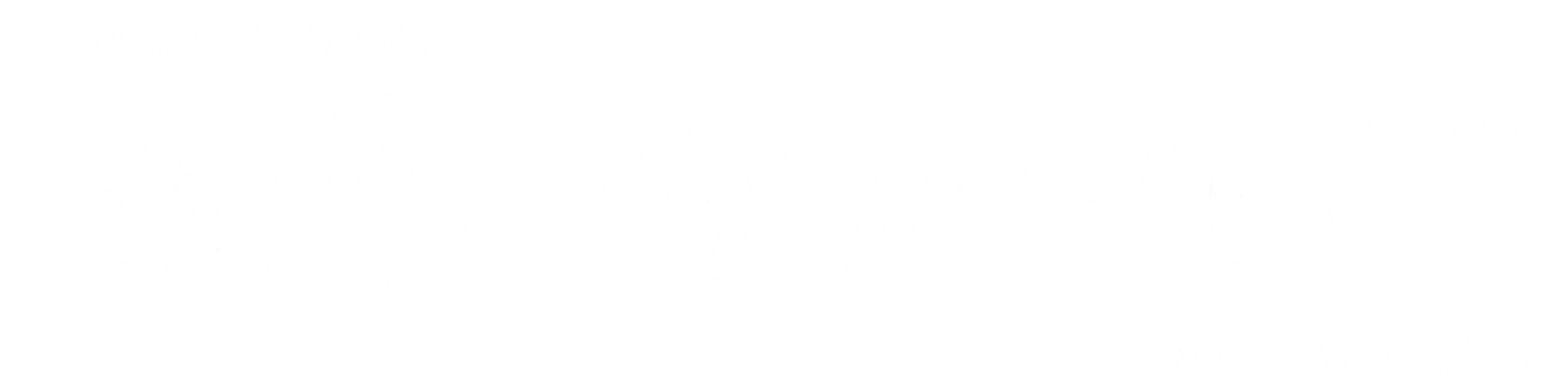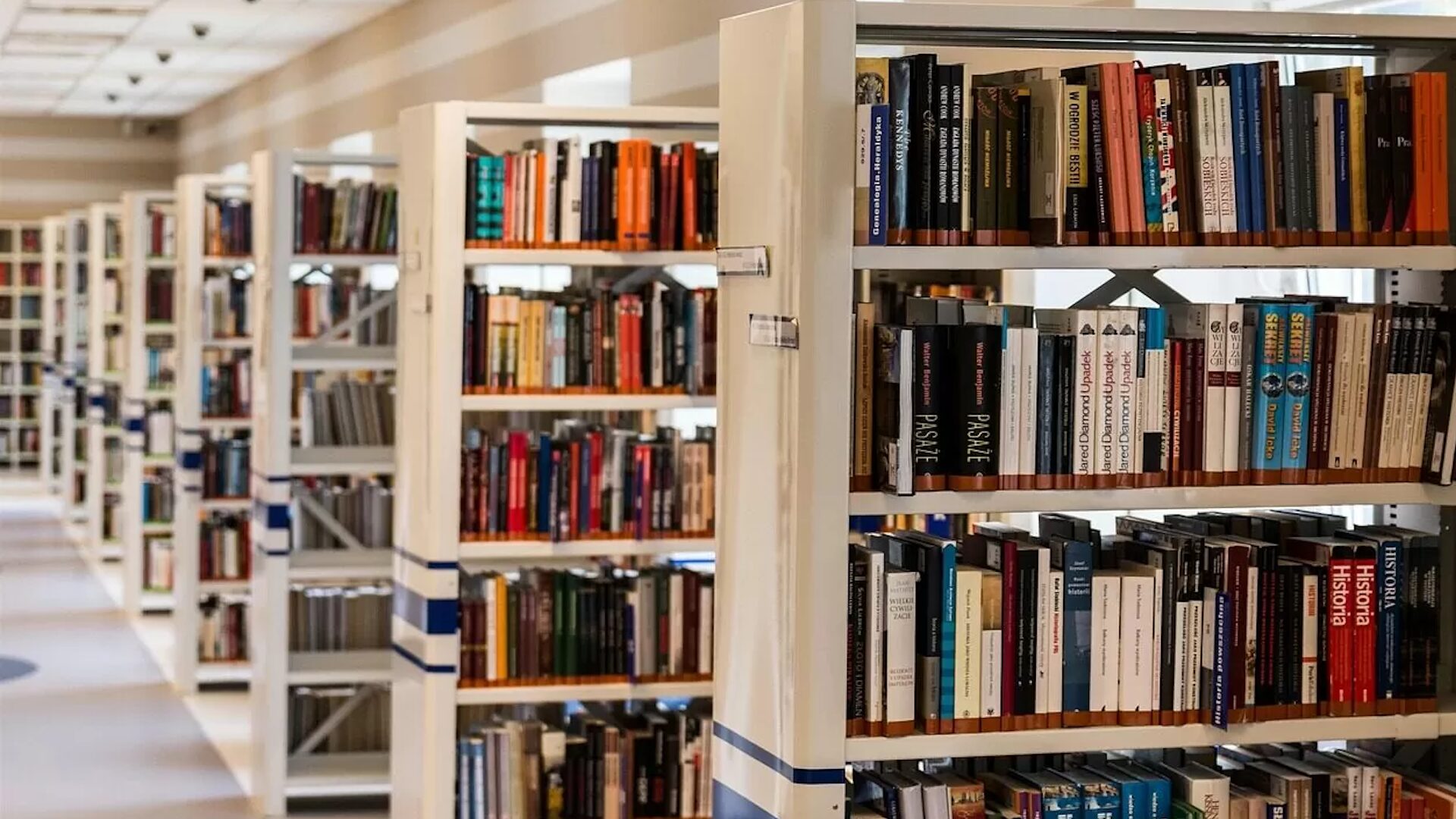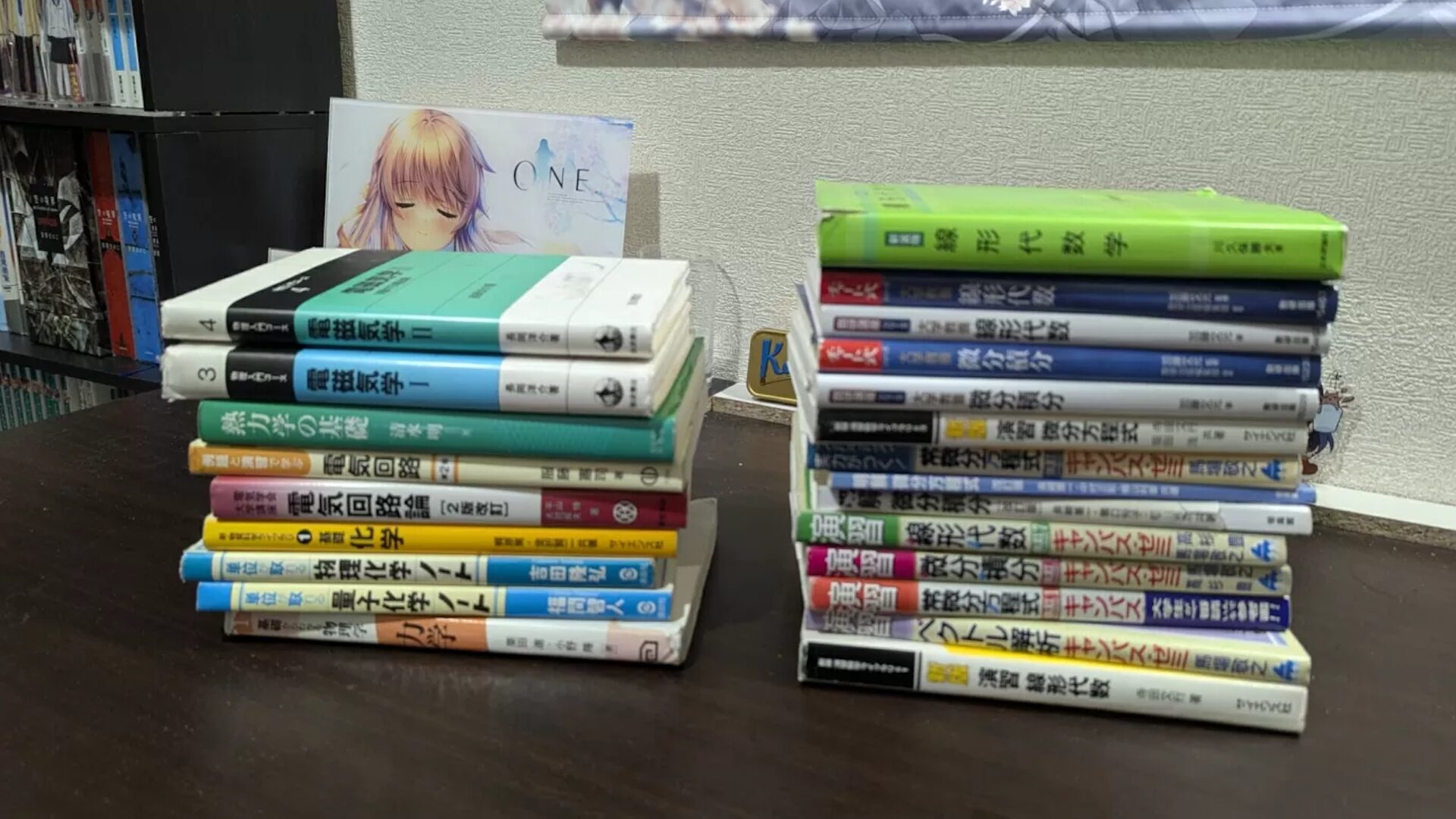浪人中の友人から連絡があった。この時分にふさわしく、共通テストの話題である。
私が大学で学業に勤しむ中、彼らも形は違えども学業に勤しんでいたのだろう。
いやはや、程度の上では彼らには到底かなわぬかもしれない。
―――人はなぜ学ぶのだろう。
ふとした疑問が頭をよぎった。
高校時代、受験のためだけに盲目的に学業に勤しんでいた一年前から一転、大学で学びの自由度が増える折、唐突にそんな漠然とした疑問が頭に浮かんだのである。
専門科目と基礎科目
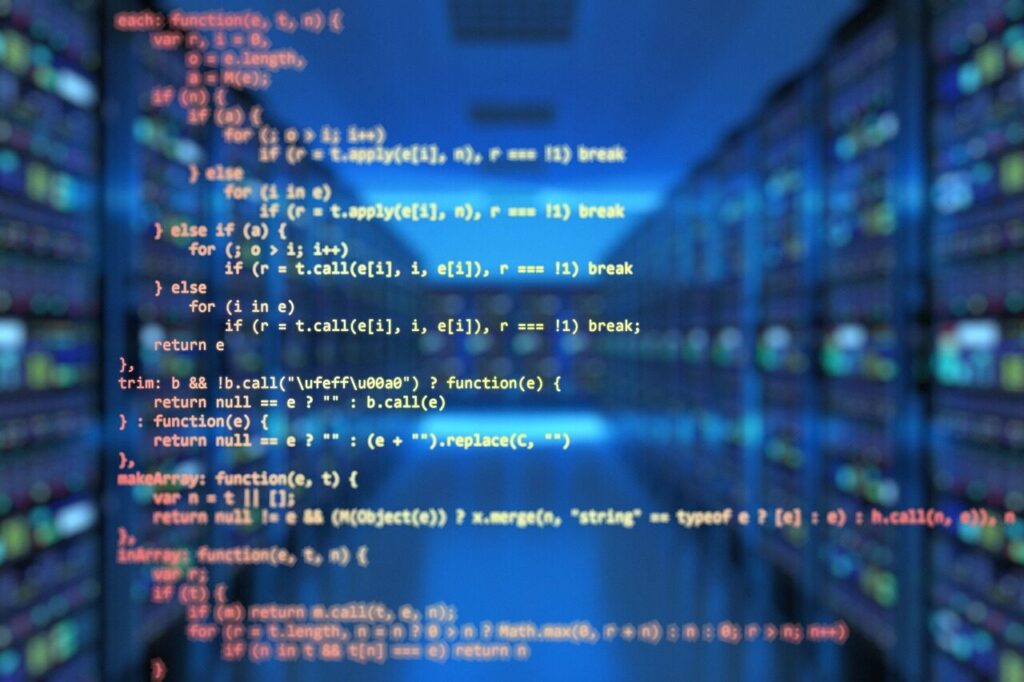
大学に入ると学びの専門性が上がるといわれる。
けれど、学部一年の身分ではあくまで高校内容に毛が生えたこと、いいかえれば専門科目ではなく基礎科目の授業が多い。
英語や第二外国語は言うまでもなく、理系であっても専門分野ではない内容が広く扱われる。
一見専門分野に関係ない分野をなぜ学ぶのだろうか。
盲目的に学業に勤しめればそのような無粋な疑問が生じることはないであろう。
けれど私の怠惰なる習慣と、専門分野に対する憧憬の念が、不幸にもこのような疑問を生んでしまった。
人は忘却する生き物だ
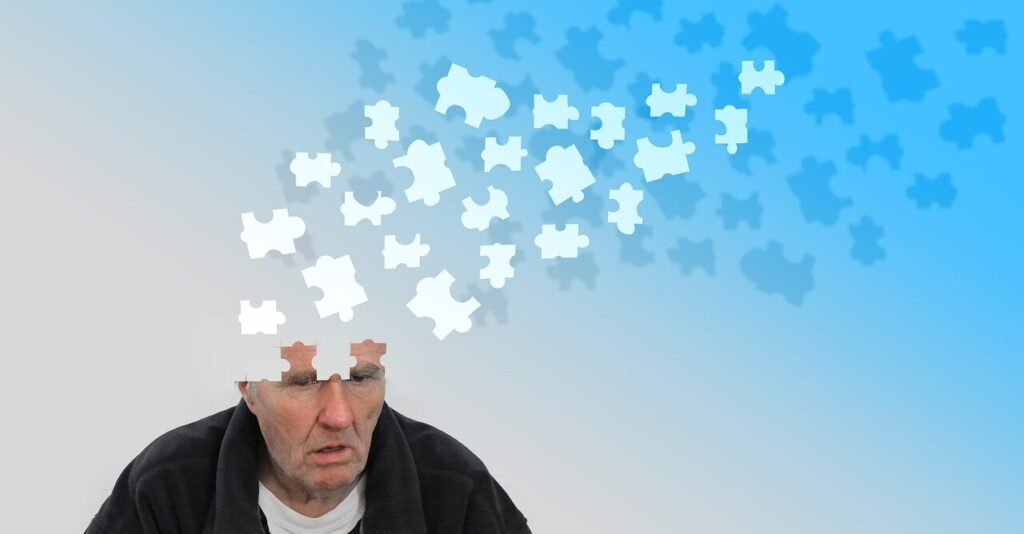
いかに学ぼうといえど、時間がたてば人はそれをほとんど忘れてしまう。
基礎科目をいかに勉強していたとしても、その後意識的に立ち返ることがなければ忘れてしまうし、なにより専門に比べて立ち返る機会というのは非常に少なくなってしまう。
忘却を恐れてなお、なぜ人は学ぶのだろう。
答えは選択肢にある

専門科目は深い学びで、基礎科目は広い学びに形容される。
言い換えれば、今後専門分野の研究をするにあたって、前者は大きな糸口をつくることであり、後者はたくさんの糸口をつくることである。
大きな糸口があれば、そこを開拓していくことは容易い。小さな、たくさんの糸口はどうだろうか。
小さな糸口は、あったとしてもそこを開拓していくことは容易くない。けれど、糸口がないこととあるけども小さいことは全く違う。
その糸口がたとえ虫食いほどの小さなものであったとしても、糸口があると「そこを開拓してみよう」という意識が生まれる。
ダンジョンを想像してみてほしい。
普通、ただの壁があったとしても、「壁を壊して進んでみよう」という気持ちには凡人はならない。
けれど、通路なり目印なり、いやはや小さな穴なりがあれば事情は違う。「何があるかわからないけど、とりあえず進んでみよう」という気持ちになれる。
たとえ学びを忘れ、糸口が矮小化してしまったとしても目印だけは残る。
知らないことと忘れてしまったことは根本的に違う。
目印があれば、人は何度だって糸口を広げることができる。
一度学んでいれば、「思い出そう」という気になれる。
専門分野での深い学びに加え、基礎分野での広い学びを大切にすることで、研究に行き詰った際に取れる選択肢の幅が大いに増える。
「選択する」という権利は学んだ者のみに与えられる。
余談

専門分野の勉強が楽しくて仕方がない。
「やらされていた勉強」を超え、「自分のための勉強」ができているような気がして、その喜びたるや…..
専門分野を学習するにつれ、研究への意欲も高まってきた。
「VR研究したい」という漠然とした目標から、さらにブラッシュアップされた、具体的な目標が浮かんできたように思う。
「東大に行きたい」という望みが、「東大で研究をしたい」という目標に変わった。
余人にはささやかかもしれぬが、私にとっては大きな前進である。
研究を志すとかならず「博士課程」というものが脳裏に浮かぶ。
研究者としては第一級の、けれど現代日本では隠遁者とも形容されうる博士号。
日本での博士に対する待遇はお世辞にもいいとは言えない。
けれど、経済的事情を差し置けば、研究のために人生を賭けるのも悪くないように思われた。
―――否、博士という名の響きの、アカデミアの探究者としての称号を、渇望せずにはいられない。
最後に
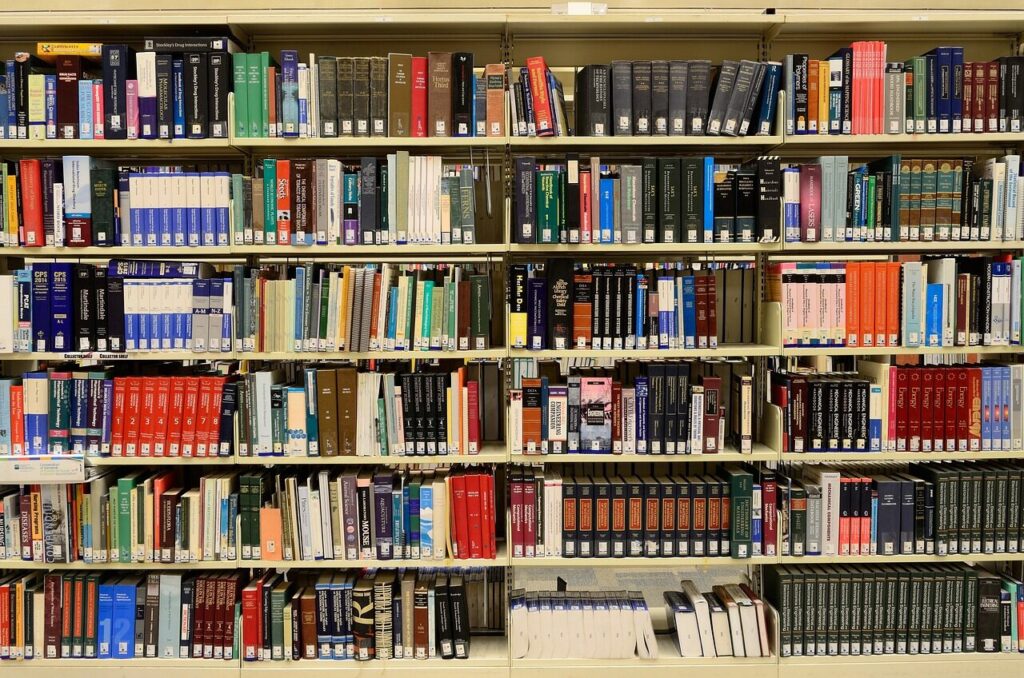
―――数年後の私はどこにいるのだろう。
―――何をしているのだろう。
―――はたまた数十年後の私は…..
夜の帳が下りる頃、あるいは深更、私は人生の妄想に耽ってしまう。
永い人生のことなどほとほと分からぬ。
ゆえに目の前のことから始めてみよう。
まずは期末テスト、よき結果をお伝えできることを切に望む。
人生に伏線を貼る…(回収されるかはわからないが。)
そのために、勉強してみよう。