開幕早々、なかなか挑発的なタイトルで申し訳ない。とはいえ、これが私の本当の気持ちである。
世に出回る教科書や参考書を中心とした書籍について、(特に受験系のものとなると)分かりやすい、或いは読みやすい、親切であることを売りにしたものをよく目にすると思われる。
そして、こうした書を手に取る多くの人も、分かりやすいこと、読みやすいこと、親切であることを要件にする傾向にあると思う。
そうした教科書や参考書が、多数のニーズに応え、また有用であることを、私自身実感してよくよくわかっているつもりではあるが、私はあえてこの潮流に逆らってみたいと思う。
分かりやすさという詭弁
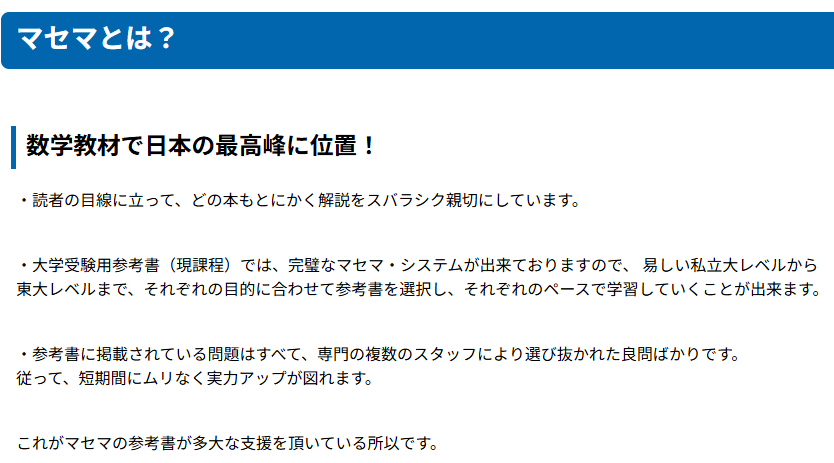
私が理想とする分かりやすさとは、「物事の本質が明快に示されていること」である。
一方、巷で蔓延している書籍には、「本質的でない部分に無用に紙面を割いた、冗長なもの」というのも多いと感じる。(怖いので例は出さないけど、何故かふとマ◯マという単語が浮かんできた。)
卑近な例
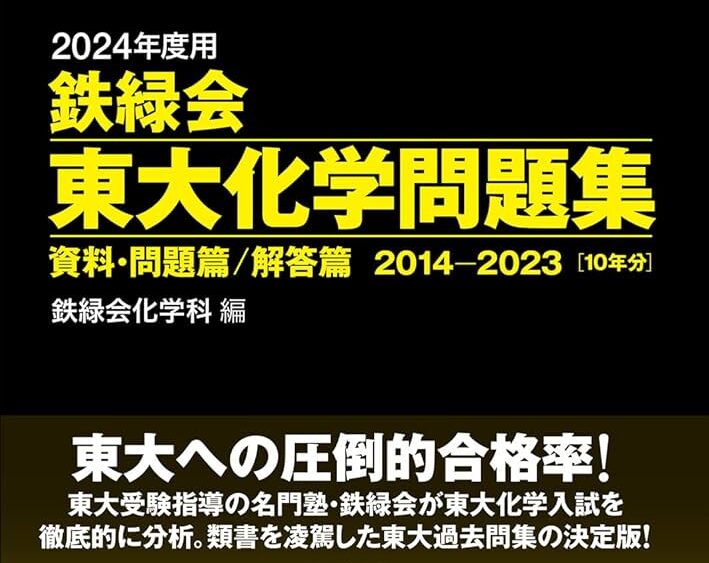
卑近な例として、それこそ受験対策用の問題集が挙げられる。
同じ問題を扱った問題集で、
①式変形がやや省略されているが、発想、着眼点が非常に明快に記されている。
②式変形を余すことなく記述しているが、発想、着眼点については淡白。
という二種類を考えてみよう。
世に跋扈する書籍の標榜する「分かりやすさ」とは、「難しいが本質的である内容をうまく噛み砕いてい解説する」ではなく、「ある程度考えればわかることを冗長に掲載する」という場合が多い気がする。
本当の「分かりやすさ」ってなんだろう

表層のわかりやすさを追い求めるがあまり、本質から逸脱し、内容が軽薄であっては、元も子もないのではないだろうか。
「分かりやすさ」という言葉の原義をここで問う意図も、私の解釈の正当性を訴える意図も毛頭ない。
ただ、表層の「分かりやすさ」だけを重要視した本は、「読みやすい」というだけの、陳腐なものに過ぎない、ただそれを伝えたいだけなのである。
咀嚼する面白さ
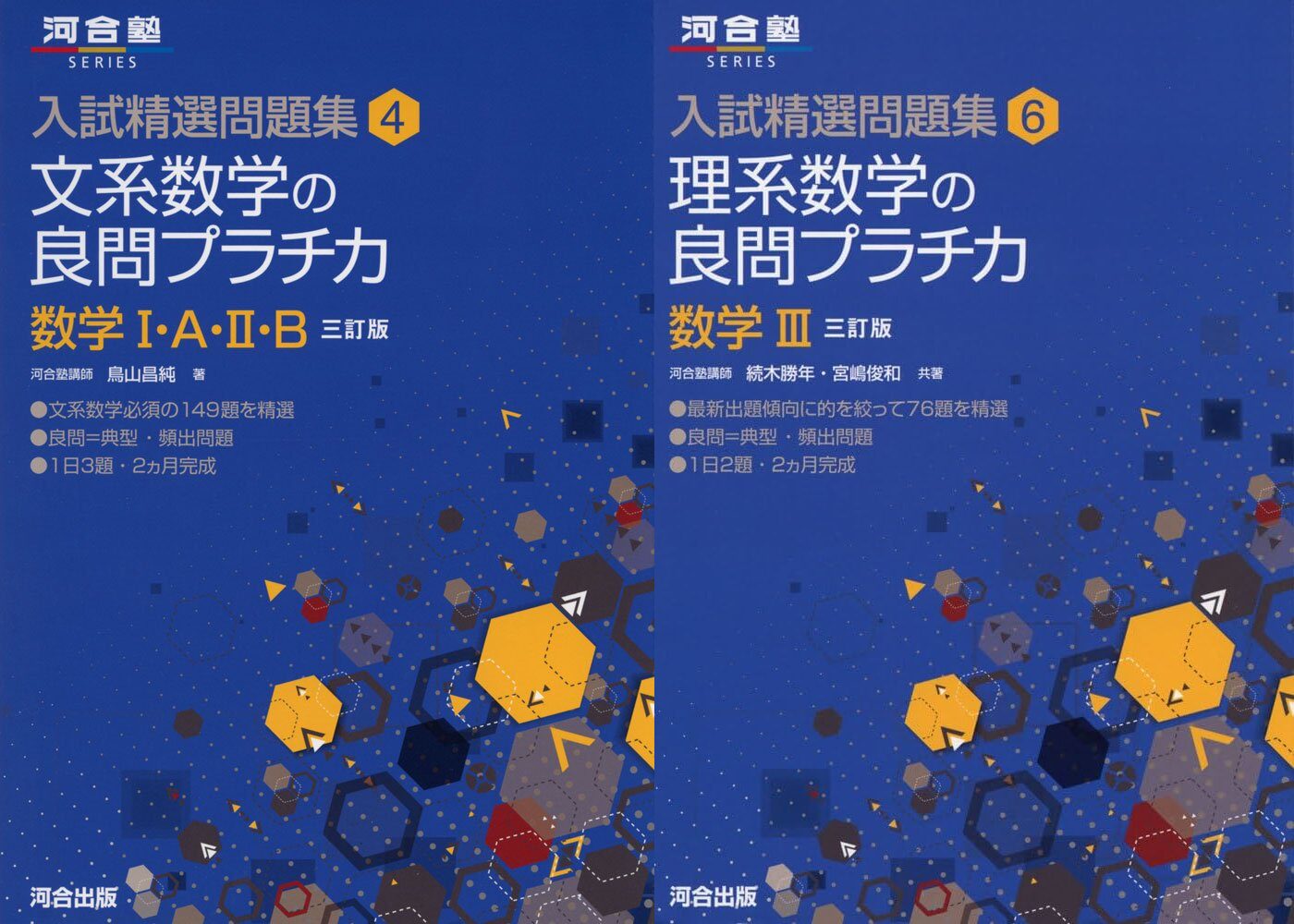
私はちょっと難しいくらいの本を読むのが好きだ。
そういった類のものは、得てして自分なりに咀嚼する必要性が出てくる。
読みやすいとはいえないものも確かに多い。
けれど、それらは、時代を超えても変わらぬような、確かな本質を穿っている。
或いは、途中式や、思考のエッセンス(それが妥当であるか否かは別問題として)を検討といった咀嚼の作業に、得も言えぬ快感を見出すことも少なくない。
本当の親切さとは
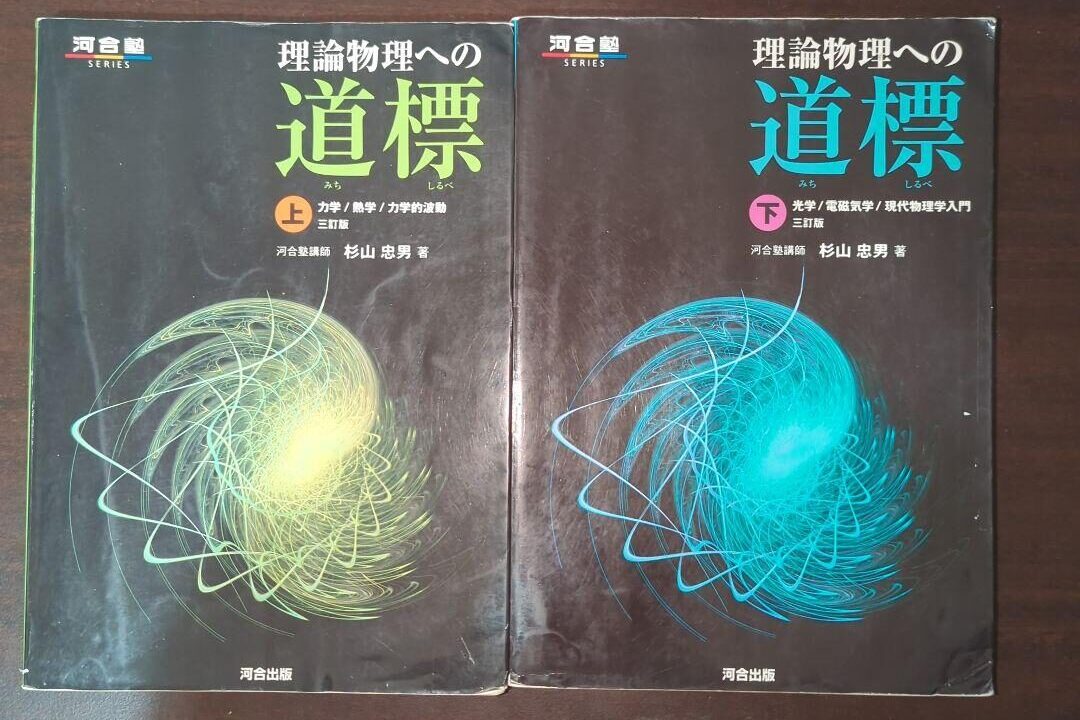
親切さとは、ただただ相手を介護するように目的地(答えといってもいいだろう)へただただ連れて行くことなのだろうか。
私は、本当の親切さとは、適切なヒントを過不足なく与え、なんとか自力で目的地へたどり着くように指導することだと思う。
多少程度の高い内容に、多少背伸びして望むことこそ本質であり、それこそが学問の面白さなのではないだろうか。
免責
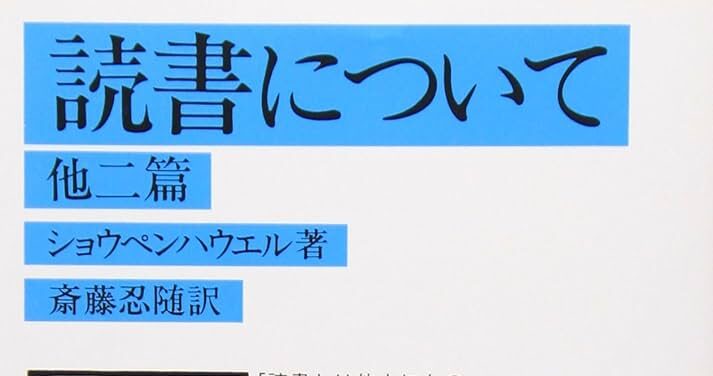
今回は参考書に限って議論を進めてきたけれども、この論法は一般にも拡張可能であると思う。
無料のコンテンツがあふれる世界で、あえて本というお金も時間もかかるコンテンツにお金を出すということ、その意義を今一度考えてみてほしい。
ここまで持論を偉そうに展開しておきながら、今更免責のようで心苦しいが、この記事が「ヒトリゴト」のカテゴリに分類されているように、以上の主張はあくまで筆者個人の見解であって、他者に意見を押し付けるものでもなければ、自分の主張の正当性を訴えるものでもない。
私自身、まだまだ学士二年という若輩であり、理論の飛躍も多いことだろう。
あくまで、未熟者の【ヒトリゴト」であることに留意されたい。(まあ要するにあまりこの記事の内容は器にしないでください。)
皆様の善き人生の傍らに、良き本がありますように。
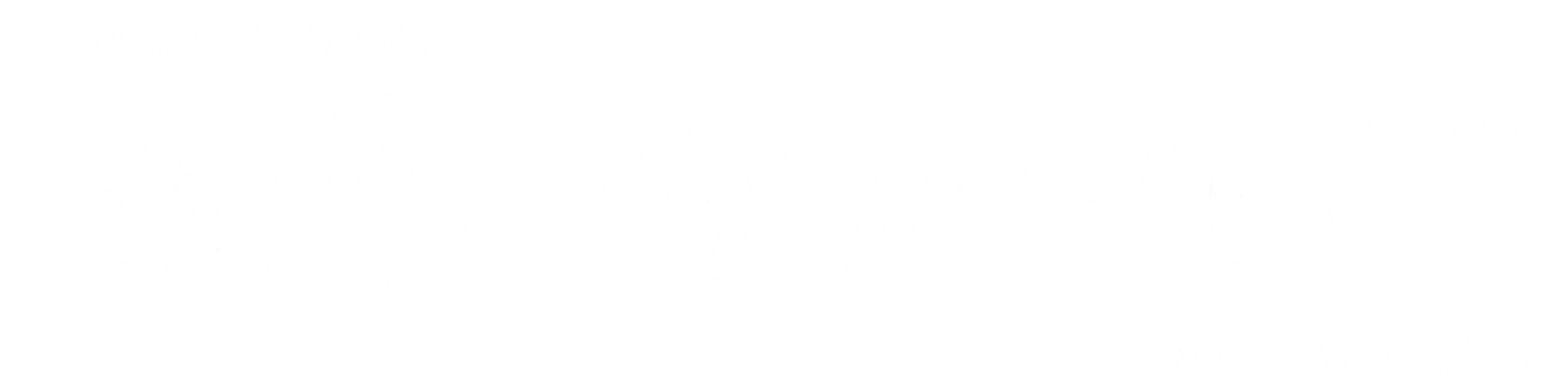
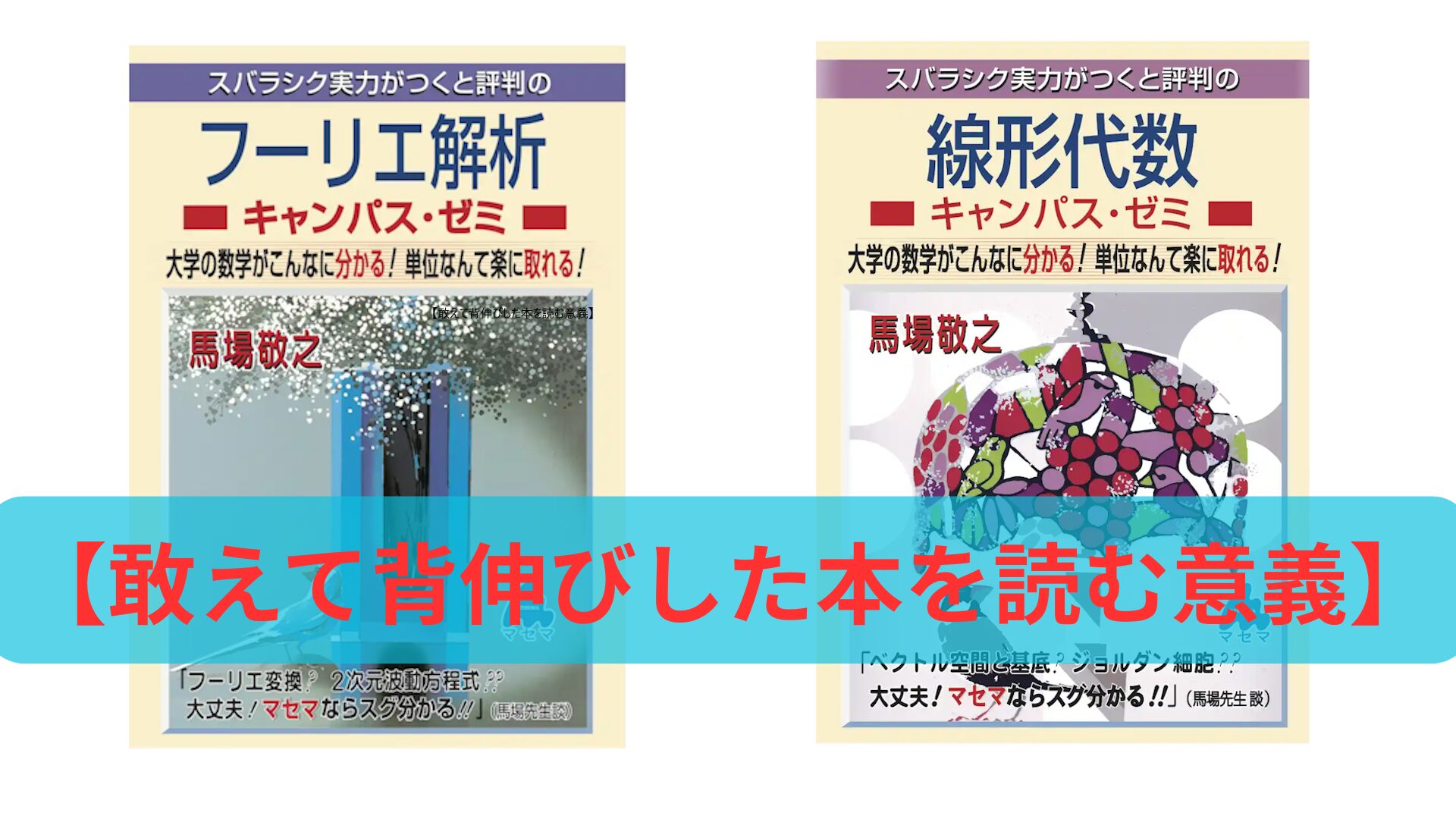



コメント